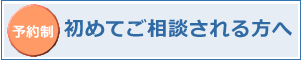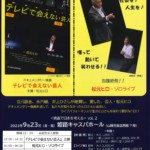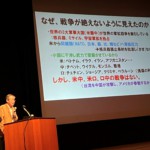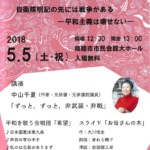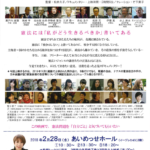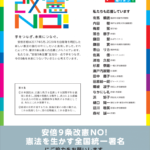| 解雇退職の問題 | 賃金の問題 | 人事異動の問題 | パワハラ・セクハラ等 | 労働災害 |
1 はじめに
•会社から突然解雇あるいは雇止めを言い渡された。
•会社が残業代や退職金を支払ってくれない。
•ある日突然、不当な配転命令あるいは出向命令を受けた。
•上司からセクハラ・パワハラを受けているが、会社に相談しても適切に対応してくれない。
•仕事中に事故に巻き込まれ怪我をした。
上記のような職場でのトラブルは枚挙にいとまがありません。
本来、労働基準法によって労働者が保護され、また労働契約法は労働契約は使用者と労働者が対等な立場における合意によって締結され、使用者の権利の濫用を禁止していますが、労働者は使用者よりも弱い立場にあるため、締結された契約自体が労働者に不利な内容となっている場合が少なくありませんし、労働契約締結過程における使用者の懲戒処分や解雇、雇止めに対して労働者が抗議しても、使用者に労働者の言い分を認めてもらうことは至難の業です。
そのような場合、当事務所の労働事件を数多く手掛けている弁護士が、ご依頼者の方の代理として交渉、労働審判、民事訴訟などの手続きを採り、解決をサポートします。
以下に代表的な労働問題について記載しておりますが、以下に記載のない労働問題についても、お気軽にご相談ください。
2 解雇、雇止め、退職の問題
解雇は、客観的に合理的な理由と社会的な相当性がなければ許されません(労働契約法16条)。「能力に欠ける」「態度や成績が悪い」「会社の業績が苦しい」という抽象的な理由で労働者を簡単に解雇することは許されません。
継続して働いてきた契約社員やパート社員の雇止めも、同じように、客観的に合理的な理由、社会的な相当性がなければ許されません。
リストラによる退職勧奨にも応じる義務はありません。辞めないと言っているのに退職を迫る退職強要は許されません。
もし解雇、雇止めといわれても、仕方ないとあきらめる必要はありません。事情を聞かせていただき、解雇が有効かどうか、弁護士が適切なアドバイスをいたします。
解雇、雇止めが無効であると考えられる場合には、事案に応じて、示談交渉・労働審判・裁判などの方法により、復職を求めたり、あるいは解決金の支払いを求めるなど、適切な解決方法をアドバイスいたします。また使用者から執拗に退職完勝を受けている場合、退職してしまう前にご相談頂ければ、使用者と折衝し、退職勧奨を止めさせることができます。
3 賃金の問題
労働時間は、原則として、1日8時間、1週40時間までと労働基準法で定められています。この時間を超えて残業をさせる場合には、使用者は残業代(最低1.25倍の割増賃金)を支払わなければならず、これに違反した場合には刑事責任が課せられる場合もあります。
しかし、サービス残業を強要され、残業代が払われない事例は、数多くあります。
このような場合、労働基準法によって計算される残業代を請求することが可能ですが、労働者が請求しても聞く耳を持たない使用者も少なくありませんし、また、使用者には労働者の労働時間を管理する義務があるのに、かかる義務を怠り、使用者がタイムカードなどによって労働時間を管理しておらず、労働時間を計算することが困難な場合もあります。このような場合に、どのように残業代を請求していくのか、どうやって証拠を収集するのかを、弁護士がアドバイスいたします。特に、賃金や残業代の請求は2年という短い時効が定められていますので、早めの相談が良い解決を導きます。
実際に請求する手段として、会社との書面による交渉、労働審判の申立て、訴訟の提起など様々な手段が考えられます。これらの手段のうち事案に適した手段を選択し、手続をすることになります。
4 配転、出向等の人事異動の問題
企業が従業員の配置の変更を行う場合に、同一の事業所内における変更を「配置転換(配転)」といいい、このうち、勤務地の変更も伴うことを「転勤」という場合があります。また、使用者が、労働者を在籍させたまま、他企業で勤務させることを出向といいます。
配転命令は、会社の裁量に委ねられる部分があるものの、不当な目的・動機をもってなされた場合、、業務上の必要性(当該人員配置の変更を行う必要性と、その人員選択の合理性のこと)をまったく書いている場合、必要性が認められても、その必要性に比べ、その命令がもたらす労働者の職業上・生活上の不利益が不釣合に大きい場合(判例では、「通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき」と表現されています)には権利濫用として無効になります。また、労働契約法では使用者に仕事と生活の調和(ライフ・ワーク・バランス)に配慮することを求めており、育児介護の問題を抱えている労働者を遠距離に転勤させるような配転(転勤)命令は無効となる可能性が大です。さらに出向命令についても権利の濫用となるような出向命令は認められません。配転、出向を命ぜられた場合にも上記のような事情から権利濫用と考えられる場合、速やかにご相談頂ければ、御一緒に適切な解決策を考えることができます。
5 パワハラ、セクハラ等の問題
上司など職場で自分よりも強い立場にある人が、その立場を背景にして職務に関連した圧迫行為を行ってくること(パワハラ)、労働上の関係を利用して行われる相手方の望まない性的な行為(セクハラ)を行うことが、職場において行われることが多々あります。特に、パワハラは、成果主義を採用する企業の増加により、一定の達成目標を設定した上司から目標達成をしきりに促されたりする過程で行われることもありますが、パワハラ、セクハラはこれを行う当事者には民事上不法行為責任が生じるだけでなく、職場でのパワハラ、セクハラを放置した使用者にも、パワハラ、セクハラを受けた労働者の良好な職場環境を維持する義務に違反したものとして、損害賠償責任が生じる場合が少なるありません。
パワハラ・セクハラいずれについても、当事務所の弁護士が事件を受任した場合には、まず使用者にパワハラ、セクハラを止めさせて労働者の職場環境を海図んすることを要求したり、慰謝料等損害賠償請求を行うことを検討します(事案によってはパワハラ、セクハラを行う当事者にも損害賠償請求することになります)。
また、パワハラ・セクハラによって、うつ病等の精神疾患に罹ってしまった場合には、労災の申請を検討します。
6 労働災害
労働者が業務上の事由により、負傷(怪我)、疾病(病気)、障害、死亡する災害のことを労働災害といいます。
労災を被った労働者や遺族は、労災保険による補償の給付を受けることができます。 しかしながら、労災として認定されるためには、その傷病等が業務上発生したものと言えなければならないとされています。
業務上発生したものといえるかは、「業務遂行性」(その傷病の原因が事業主の支配下にあること)が満たされ、かつ「業務起因性」(相当因果関係)が必要と考えられています(行政解釈)。
そして、一見して業務起因性が明らかでない傷病(例えば過労死等)の場合には、労働基準局監督署も業務起因性を否定することが多く、労災申請が却下されてしまうこともあります。
このような場合には、各都道府県労働局におかれている労災保険審査官に不服申立を行い、さらには厚生労働大臣の所轄のもとにある労働保険審査会に、再審査請求を行うことができます。
労災からの保険給付は業務上の災害にあった場合、事故の発生につき使用者に過失があるかないかを問わず認められることになりますが、事故の発生について使用者に過失が認められる場合には、使用者に安全配慮義務違反に基づく損害賠償責任が生じ、労災保険の給付の問題とは別に、使用者に上積み補償を求めることが可能となります。